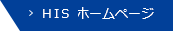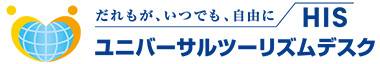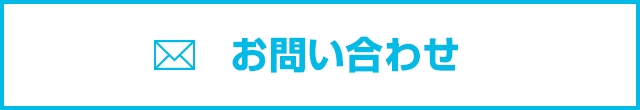文字サイズ
スタッフブログ
夏のオランダ・ベルギー旅行7
ANAで行く!オランダ・ベルギー8日間のお時間です。
お待たせしました!←
5日目
旅も後半です。
アムステルダム市内観光へ繰り出しましょう。
スケジュールには国立美術館、中央駅、ダム広場などとあります。
「など」などってどこだ。
「など」は一旦、見なかったことにしましょう。
観光しましょう。観光。
アムステルダム国立美術館

公式ホームページには以下の記載があります。
「アムステルダム国立美術館はこのたび、中世・ルネッサンス期から20世紀までを網羅した、オランダ芸術と歴史の旅をコンセプトにコレクションを展示します。コレクションは時系列に沿って旅し、時のうつろいと美しさを感じることのできる初の試みです。
オランダの物語が、周りを取り巻く国々の状況と共に、4フロアにわたって年代順に語られます」
時のうつろいと美しさ・・・いったいどんな感動が待っているのでしょうか。
こちらの美術館ではフェルメールの絵画は4点所蔵しています。
レンブラントは有名な「夜警」が展示されています。
レンブラント没後350年の今年(2019年)レンブラント・イヤーとして企画展やイベントを通じてレンブラントを讃える1年となるそうです。
また、「夜警」は7月から修復プロジェクトが始まり、その修復作業は一般公開されます。
見れます、修復作業。
ゴッホの「自画像」も見逃せません。
アムステルダム中央駅

wikipediaから引用してまとめると
アムステルダム中央駅の駅舎は建築家P.J.H.カイペルスとA.L.ファン・ゲントによって設計。
カイペルスは国立美術館を設計した実績を持つため起用された。
ネオゴシックとネオルネサンスを融合させた様式であり、国立美術館とは強い類似が見られる。
駅舎の中央には駅を「新たな港」の象徴とすべく2本の塔があり、これが国立美術館との類似を際だたせている。
2006年4月11日、東京駅とアムステルダム中央駅は姉妹駅となった。
はい、、つまり、、ええと、、国立美術館と中央駅の類似と違いを楽しもう。ということですね。
東京駅はアムステスダム中央駅をモデルとしたという説もありますが、アムステルダム中央駅はネオゴシック様式、東京駅はビクトリアン様式と違いがありその説は否定されつつあるようです。
日本もそうですしヨーロッパもその他の地域もその絵画や建築の様式からどのようなものが好まれ、そして繁栄と移り変わりが見て取れてとても楽しいですね。
ダム広場

もとはアムステルダム川をせき止める堰のあった場所でアムステルダムの語源となった場所です。
ダム広場は王宮、新教会、マダム・タッソー館、国立モニュメントなどに囲まれています。
きっと、スケジュールにあるダム広場などの「など」はこのダム広場の周りの事をさしているのでしょう。
お時間と状況によってどこを見て回れるのか、当日のためにいくつかご紹介してまいります。
王宮

1648年~1655年に建設された旧市庁舎。
なぜ王宮と言われているかというと、ホラント王国時代の1806年から1810年、ナポレオン1世の弟であるルイボナパルトの宮殿として利用されていました。
現在は迎賓館として利用されています。
新教会

新ということは、もちろん旧教会もあります。
街の発展に旧教会だけでは対応しきれず1380年~1408年に建設されました。
1645年の火災で焼失していますが、その後再建され、現在はプロテスタントの教会になっています。
国立モニュメント

第二次世界大戦の戦没者を追悼する目的で1956年に建てられました。
マダム・タッソー・アムステルダム
ロンドンにあるマダム・タッソーのイギリス国外発の分館です。
デ・バイエンコルフ
アムステルダム最大の老舗百貨店
ニューウェンダイク通り
アムステルダム中央駅からダム広場までの歩行者天国の通りです。
両サイドにお店が並び、いつでもに賑やかな通りです。
ダム広場周辺を後にして、
アフスライトダイクへ向かいましょう。

アフスライトダイクはオランダ北部にあるアイセル湖と北海(ワッデン海)を仕切る世界最大の堤防です。
なぜ堤防を築くことになったかというと、農地を増やすためにワッデン海の南半分を仕切り、水を淡水化し、海面を下げ農地を増やす大干拓事業のためでした。
その事業は現在は永久中断中とのことですが、ワッデン海の湾を大回りせずに移動できるとのことで、交通には非常にメリットをもたらしています。
6日目はアントワープ市内観光からブリュッセルへ
です。
ツアー詳細はこちらデス。